AICU mediaでは生成AI時代に「つくる人をつくる」を推進しつつも、これまでも「生成AIの社会と倫理」や「生成AIクリエイター仕草」といった自主規制を扱ってきました。ここで動画生成AI「Sora 2」を始点に、AICUメディアの編集長による社説(Editor's Voice)を掲載します。
https://j.aicu.ai/MagV3
世界を揺るがした2022年8月の「Stable Diffusion」のオープンリリースから、画像生成AIを解説し続けて約3年が経ちました。初期のモデルと異なり、後継のSDXL以降の Stability AI社 のオープンモデルでは、クリエイターが学習データから自身の作品を除外申請できる「オプトアウト」の仕組みが導入されました。つまり「問題がある画像があれば、こちらから学習対象から外してください」という申請サイトと「Have I Been Trained?」というツールによってオプトアウトを実現しています(なお、現在は haveibeentrained.com は動作していません)。
https://j.aicu.ai/SBXL
一方で、Sora2のオプトアウトはどうなっていますでしょうか。たしかに「フィルタリング」や「サードパーティの権限」といったメッセージによって生成できなくなった種類の動画は増えています。もちろん、パロディ動画やフェイクニュースのような作品は最近のSora2ではあまり多くはなくなっています。注目すべきはシーン生成能力であり、それはすでにユーザー開発ツールを紹介しています。
蹂躙:「Sora 2」が仕掛けた"三方向の挑戦状"
OpenAIが2025年9月30日に発表した動画生成AI「Sora 2」は、単なるバズり動画を生成するサービスや技術革新ではなく、日本の法制度に対する意図的な挑戦であったと筆者は考えています。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/aistream/2052295.html
この挑戦は、本連載の以前の記事で、すでに"三方向の挑戦状"として整理しました。
-
肖像・声の権利: 「カメオ」機能による肖像権、および声優の実演家の権利(著作隣接権)の無視。
-
リミックス文化の強要: 米国型「フェアユース」的なリミックス文化を前提とした設計による、日本の「同一性保持権」への抵触。
-
法的地位の空白への攻撃: 著作物性が曖昧なAI生成物を「無料アプリ」で大量生産させ、法的救済を困難にする「マッシブ攻撃」。
①肖像・声の権利: 「カメオ」機能による肖像権、および声優の実演家の権利(著作隣接権)の無視
Soraは初期ユーザーに対し、顔画像をキャプチャして3次元的なデジタルダブルを生成し、共有することができます。肖像権の再利用は本人による許諾制ですが、そのリアルなキャラクターが喋る際の「声」は出自が不明です。日本では現在、「声の権利」が法律で明確に定義されておらず、声優やナレーターは法的に脆弱な立場に置かれています 。特定の声に対する実演家の権利や、楽曲(そのままの楽曲が出てくることがあります)については権利が不明瞭です。
この動画は「鹿せんべいと戯れるサムアルトマン」ですが、「鹿せんべい」といった日本特有の(あるいは「ニッチな」)素材を学習している点から、意図的に日本の文化や食といったデータを学習している可能性があります。声についても、声優ファンであれば元の声を言い当てることができるレベルで明瞭な生成がなされることがあります。
②リミックス文化の強要: 米国型「フェアユース」的なリミックス文化 を前提とした設計による、日本の「同一性保持権」への抵触
本連載の読者の皆様に「日本にはアメリカのような包括的な『フェアユース(公正利用)』の規定はありません」という話はもはや「釈迦に説法」かもしれませんね。日本の著作権法第32条の「引用」など、個別の例外規定として認められるには、主従関係の明確化、明瞭な区分、出典の明示といった要件を満たす必要があります。
音楽分野で文化として醸成された「リミックス」を動画で実現したSora2の技術力には感服しますが、日本の著作権には著作者の意に反して勝手に変更・改変されない権利、「著作者人格権」があります。同一性保持権、つまり著作者からみた第三者に「自分の著作物やタイトルを変更されない権利」です。これは財産権ではありませんが、「お気持ちを主張してよい」という「心の権利」がある点が日本法の特徴です。
「ガルパン」もしくは「ガールズアンドパンツァー」という単語を意図して使わなくても、特徴のある色やロゴ、キャラクターデザイン、3DCGが生成されます。たしかにパロディ動画として笑えるのですが、許諾を得ているわけではありませんし、原作に思い入れがある方にとっては不快かもしれません。私にも「面白ければいいじゃないか」という気持ちもあったころがあるのですが、初代ガンダムで女性キャラを使った度を超えたパロディなどを見ると不快に思いました。例えば「ウマ娘 プリティーダービー」には明確な二次創作ガイドラインがあります。日本のオタクにはルールを守って二次創作を楽しむ文化があります。
ウマ娘 プリティーダービー 公式ポータルサイト
https://umamusume.jp/derivativework_guidelines/
③法的地位の空白への攻撃: 著作物性が曖昧なAI生成物を「無料アプリ」で大量生産させ、法的救済を困難にする「マッシブ攻撃」
そもそも上記の通り、明確に著作権法やその他の法律に抵触しており、非常にカジュアルな方法で「AI海賊版動画製造サービス」として利用することも可能である「Sora2」ですが、OpenAIのようなブランドを確立したポジションにいるユニコーン企業が日本市場において無料アプリを使って大量にグレーゾーンを越境してくると、IPステークホルダー各位にとっては「オプトアウト」で対応するにも人的な労力が追いつかない現状は、想像に難くありません。
また、3月にリリースされたChatGPT画像生成による「ジブリ化」は記憶に新しいです。西海岸、特に北米スタートアップ界隈が集まるサンフランシスコでは「赤信号をみんなで渡れば怖くない」「日本のユーザーもたくさん使っている」といった話題が交わされていました。筆者が関わるクリエイティブAI業界においては、この「日本の牙城をいかに崩すか」にベットしている投資家もそこそこにいると感じています。彼らは日本のアニメを中心とした「名前タグ」(特定のIP名で学習させている)や類似性・依拠性の高い画像生成を売り物にしており、「日本からもたくさんのユーザーが利用している」と鼻息荒く投資家から資金を集めています。このあたりはAI時代の「カリフォルニア南北戦争」として紹介してきました。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/aistream/2023376.html
「著作権法うわのソラ作戦」の先にある「AI税」と「AI貿易赤字」のダブルパンチ
利用規約を素直に読めば、「オプトアウト」で問題がある動画に対応するとのことです。しかし利用者視点での体感では、米国のIP(アイアンマンなど)はブロックしつつ、日本のIP(ジョジョ、初音ミクなど)は生成可能でした。この「差別的フィルタリング」こそが、日本市場と法制度が「蹂躙された」証拠であると認識せねばなりません。オプトアウト申請は、個々の作品を延々と申請し続けなければならない、まさに骨の折れる“無償労働”です。さらに、ウェブサイトのクロール(情報収集)を拒否するrobots.txtといった技術的手段も、AI開発企業に無視されるケースが報告されており、その実効性すら盤石ではありません 。
https://privacy.openai.com/policies
作家としてこの手の作業をすることもあるのですが、沢山の作品があればその申請の回数も多くなります。販売するために申請作業をするならともかく「本来権利を持っているのは僕なのに…」と思いながらボランティア作業をさせられる印象があります。オプトアウトすることによって収益が増えるわけではありませんからね。ただでさえサブスクリプションやGPU代、API費用などを支払っているAIクリエイターとしては、AI貿易赤字になりがちなのに、オプトアウトでお気持ち表明のボランティア活動をさせられるかと思うと「もっとスマートな方法ないの?」と感じます。
実は日本に存在する著作権による報酬制度
サム・アルトマンは「報酬制度」をブログで触れていますが、実は日本では2018年の著作権法改正によって創設された「授業目的公衆送信補償金制度」で報酬制度を実装しています。そしてこれは、生成AIをめぐる新たな搾取「無償労働」の問題も生んでいます。これは抽象的な未来の懸念ではなく、その構造的な欠陥は、日本国内の既存の著作権制度の中に、すでに具体的な形で現れています。「授業目的公衆送信補償金制度」の管理団体である一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、GIGAスクール構想に代表される教育のデジタル化を背景に、オンライン授業などで教員が著作物を円滑に利用できるようにし、同時に著作権者等に適切な対価を還元するという、極めて正当な目的のために設計されました。
SARTRASの仕組みは、一見すると合理的です。大学や教育委員会といった教育機関の設置者が、在籍する児童・生徒・学生一人当たりの補償金(例えば、2021年度は小学生で年額120円、中学生で180円)をSARTRASに一括して支払い、教員は授業の過程で、個別に著作権者の許諾を得ることなく、著作物を公衆送信(例えば、授業資料をサーバーにアップロードしたり、オンライン授業で画面共有したり)することが可能になります。これはオプトインもオプトアウトも不要です。SARTRASは、集められた補償金を、JASRAC(音楽)やJRRC(出版)といった各分野の権利者団体に分配し、そこから個々のクリエイターに対価が支払われるという流れです。
しかし、問題はその申請方法と分配方法にあります。集められた補償金を、どの権利者に、どのような比率で分配するのか。その根拠となるデータは、全国の教育機関からの全数調査ではなく、無作為に選ばれた約1200校の「サンプル校」からの利用実績報告に依存しています。この一点に、制度の構造的欠陥と、「無償労働」の問題が凝縮されています。サンプル校に指定された教育機関、とりわけ現場の教員に課せられる報告プロセスは、善意の制度がもたらす意図せざる管理的負担の典型例です。教員は、オンライン授業で利用した著作物について、専用のオンラインフォーム「TSUMUGI」を用いて、極めて詳細な情報を入力しなければなりません。その報告項目は多岐にわたります。2021年度の報告では、主に以下の13項目が要求されています。(1)教科等名・授業科目名(2)学年(3)履修者等の人数(合計)(4)著作物の入手・掲載元の分類(書籍、ウェブサイト、放送など)(5)著作物の分類(文字・文章、写真、美術、図表、音楽など)(6)著作物の入手・掲載元名(書籍名、ウェブサイト名など)その他、著作者名、利用部分、公衆送信の態様などです。
このリストを一見するだけでも、その煩雑さは想像に難くないでしょう。しかし、最も過酷な負担を生み出しているのは、「多重入力(The Multi-Entry Problem)」問題です。例えば、ある歴史の教科書の1ページを授業資料として生徒のタブレットに配信したとします。そのページに、本文(文章)、古文書の写真、そして合戦の様子を描いた絵図が含まれていた場合、教員はこれを一件の利用として報告することはできません。本文の著者、写真の撮影者(あるいは所蔵者)、絵図の作者がそれぞれ異なる権利者である可能性があるため、これは「文字・文章」「写真」「美術」という3つの異なる著作物の利用として、それぞれ個別に、著作者名等を特定した上で報告しなければならない現状があります。この作業は、教育という本来の専門性とは全く異質の、高度な著作権管理業務に他ならず、教員は、授業準備や生徒指導の時間を削って、この複雑なデータ入力作業に従事することを強いられます。これは、制度を維持するために現場の教員に転嫁された、対価の支払われない管理的労働、すなわち「無償労働」そのものです。
現在のアプリ版「Sora」はリリース直後に比べ、次第にブロックされるIPが多くなり、現在では本来のカメオ機能でパロディ動画をつくるよりも、オリジナルの動画をつくることに活用しているユーザーが多いです(筆者もかなり面白いものを作れるようになってきました)。
最近ではオラクルちゃんというオリジナルキャラクターのカメオを作った開発者がいます。実在の人物しか作れない設計のカメオを非実在(非自然人)キャラクターが作ったとして、この報酬や対価、責任はどこにあるのでしょうか。
公式として「オラクルちゃん」をSora2で「キャラクターカメオ」登録しました!
— 開発者 T (@__t__ai__) October 30, 2025
「アットマークoraclechan」で皆さんも気軽にオラクルちゃん動画を作りまくることが可能です!
ぜひキャラクターカメオのテストとして動かしてみてください! https://t.co/lSxLX6C0iN pic.twitter.com/3FSXjuqAQ8
当初のサム・アルトマンのブログによれば「日本のユーザーの創造性を賞賛」しつつ「報酬制度をつくる」という精神を善処的に捉えれば、整備されているSora2APIが利用されるべきでしょう。12秒で500円超えという高価なAPIですが、上記のSARTRASの「TSUMUGI」に入力するのに比べればかなり合理的です。
実際のところ「バズるパロディ動画」や「フェイク動画」を無償で作れるプラットフォーム、という立ち位置は、OpenAIやSoraが目指すべき立ち位置なのでしょうか。オープンモデルで利用者が各自の責任において利用するのと異なり、有料のAPIやサービスなのであれば、著作権を解決し、依拠する原作を信頼感高く使えなければ、「Sora」の価値は半減以下でしょう。もちろん画像生成AIの使い手として見た時に、Sora2の世界シミュレーター、シーン生成技術などは素晴らしく、生成した動画自体に価値があります。コミュニティが開発してくれた素敵なツールを使えば、他の画像生成ツールにも便利に使える補足的なモデルとして有用です。とにかく学習元さえハッキリしてくれればな、という切なる思いがあります。
🔶「Sora2 Frame Splitter」はSora2の生成動画をカット割りに使えるツール、しかも無料でオープンソース!
https://corp.aicu.ai/ja/sora2-frame-splitter-20251028
サム・アルトマンがいうような「報酬」は本来、このような便利なツールを開発する人々や、基盤モデルの学習元素材である原著作に還元されるべきで、そのトレーサビリティ技術やログ、監査などOpenAI側にはそれらを可能にする技術があるはずです。そうでなければサブスクリプションとして「AI税」のような徴収をする立ち位置ではありません。
月額の利用料金を支払い、著作権解決を行うという視点では、音楽生成サービス「Suno」と「Udio」が大手レコード会社から著作権侵害で提訴された問題があります。主な争点は、AIが既存の著作権保護された楽曲を無断で学習データとして使用したかどうかです。RIAA(全米レコード協会)が訴訟を主導しており、AIによる著作権侵害の規模と影響が問われていますが、実際、楽曲生成で様々な音楽を生成し、収益化を達成しているユーザー視点では「きちんと著作権を解決してくれているなら支払う価値がある」という印象を持っています。
クリエイティブAIの未来に「AI税」があるのであれば、そのルールを作るのは国であるべきでしょう。そしてその文化圏の「年貢」を支払うべきは受益者であるOpenAI側ではないでしょうか。クリエイターは受益者でもありますが貢献者でもあります。特に改正しなくても、著作権法はこれまでもこれからも、クリエイターをまもり、育てるエコシステムとして機能します。法整備はそのためにあるのではないでしょうか。今はこの「文化の上流」をきちんと押さえなければならないタイミングです。
学習元がなければパロディ動画はつくれません。無断学習は、AI開発を念頭に2018年に改正された著作権法第30条の4で、一定の条件下では可能と解釈されがちです 。しかし、この条文が制定された当時、Sora 2のように既存の商業作品と直接競合しうる高品質なコンテンツを、誰もが大規模に生成できる未来は想定されていませんでした。だからこそ、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は例外とする“但し書き”が今、極めて重要な意味を持つのです 。利益独占企業であればなおさら、この「非享受目的」であることを説明することが難しくなります。
反撃:2025年10月下旬、日本が上げた"三本の狼煙"
「潮目」の変化
この「蹂躙」に対し、2025年10月最終週、日本は無力ではありませんでした。抽象的な法解釈の議論は終わり、「潮目」が変わりました。法務・政治・市場の三方面から、明確な"反撃の狼煙"が上がったことを記録しておきます。
狼煙(1)法務・産業界の結束:CODAの要望書(10月27日)
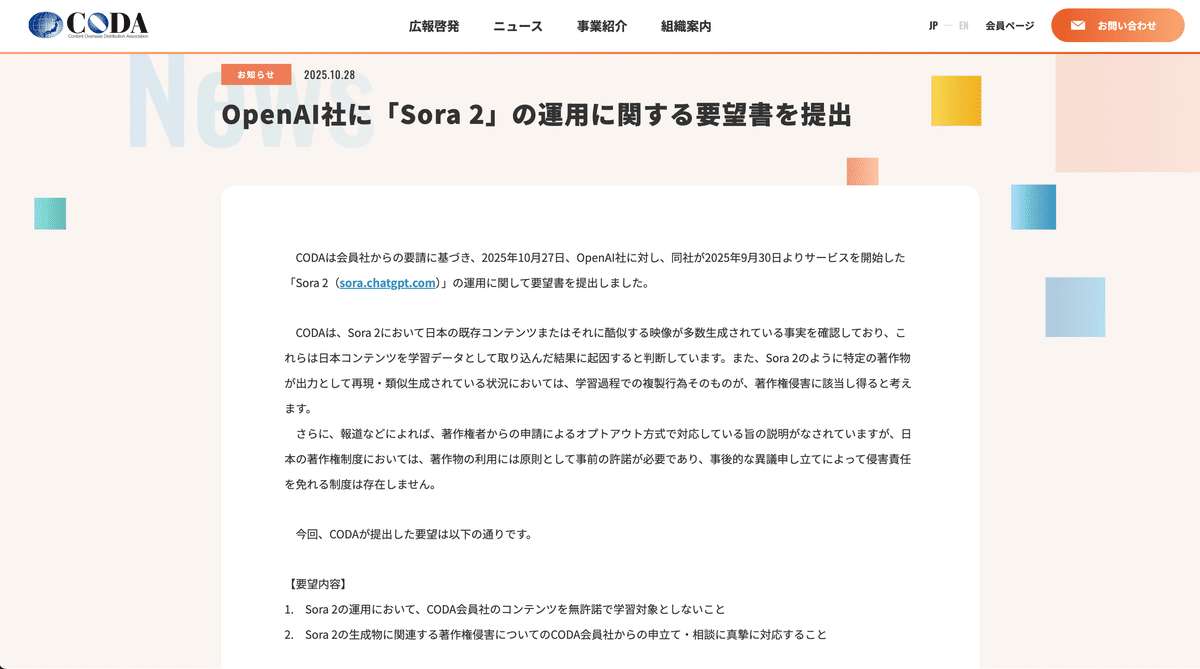
CODA(一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構)がOpenAIに提出した要望書(https://coda-cj.jp/news/2577/)によると、要求は以下のシンプルな2点です。
-
Sora 2の運用において、CODA会員社のコンテンツを無許諾で学習対象としないこと。
-
Sora 2の生成物に関連する著作権侵害についてのCODA会員社からの申立て・相談に真摯に対応すること。
これは単なる「お願い」ではありません。「オプトアウトは日本法上無効であり、事前の許諾が必要である」こと、そして「特定の著作物が類似生成される場合、学習過程の複製行為そのものが侵害に該当し得る」という、著作権法第30条の4の「但し書き」に踏み込む、明確な法的立場の表明であると考えていいでしょう。
狼煙(2)政治・行政の介入:小野田知財担当大臣の発言(10月28日)
小野田内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策、人工知能戦略、経済安全保障)、経済安全保障担当、外国人との秩序ある共生社会推進担当が、OpenAIとの対話と「オプトイン方式」への変更要請を公言したことが報じられました。
政府は同社に対し、事前にキャラクター使用などの同意を得る「オプトイン方式」をとるよう要請している。
小野田氏は「著作権侵害となる行為を行わないように要請を行う、事務方においてオープンAIとの対話を密に行っていると承知している」と説明。「オプトイン方式への変更を含み、オープンAIの対応について、引き続きデジタル庁を含む関係省庁と連携をしながら、政府全体で同社に対し適切に見直されるように注視していく」と語った。
スケジュール感を問われ、「イノベーションの促進とリスクの対応のバランスは、AIの戦略の中で非常に重要だと思っている。アニメや漫画のクリエイターが創造性を最大限発揮できる環境を整えていくのは非常に重要だが、具体的なスケジュールというよりは、やるべきことを一つ一つ(やっていく)」と述べるにとどめた。また、「著作権を持っている民間企業でもしっかりとやってほしい」と呼びかけた。
産経新聞のまとめではわかりづらいので以下の資料から実際の記者会見を確認することをお勧めします。
政府広報オンライン:小野田大臣記者会見(令和7年10月28日)
7:45ぐらいからニコニコ動画の七尾氏によって質問されています。
https://www.gov-online.go.jp/press_conferences/minister_of_state/202510/video-303783.html
小野田大臣:デジタル庁に任せていたわけではなく、前大臣より内閣府として進めており著作権侵害を行わないよう要請を行う。OpenAIとの対話を密に行なっている。オプトイン方式への変更と連携、見直されるように注視していきたい。さらに著作権を持っている方々、日本の「AI法」イノベーションの促進とリスクのバランス、クリエイターが創造性を最大限に発揮することは大事だが、デジタル庁と連携しながら、著作権をもっている民間企業の方々もしっかりやってほしい。
七尾氏:ディズニー/MidJoruney訴訟では、「フェアユース」を盾にMidJoruneyは反論しているが。
小野田大臣:日本だけでなく世界各国で問題になっている。裁判の判例を注視しながら整備がどのようにできるのか検討していきたい。
これは、政府が本件を単なる民間トラブルではなく、国の「かけがえのない宝」を守るための知的財産戦略・経済安全保障の問題として位置づけ、政治的意思をもって介入したことを意味します。一方で「民間企業でもしっかりやってほしい」という発言からも、単なる法整備やOpenAIへの対応ではなく、IPステークホルダーに対して「いうべき事、求めるべきことはきちんと対話してほしい」という姿勢にも見えます。これまでもデジタル庁・平大臣が中心に進めてきていましたが、前大臣・城内実 経済安全保障担当大臣、人工知能(AI)戦略担当大臣に加えて、ゲーム開発の産業などにも理解がある小野田大臣が加わったことは日本にとって大きなプラスになると考えます。
https://www.digital.go.jp/speech/minister-251007-01
狼煙(3)市場・技術の対抗:NTT西日本「VOICENCE」発表(10月27日)
"三方向の挑戦状"の一つである「声の権利」の根本的な課題に対し、NTT西日本が具体的かつ強力な技術とサービスをリリースしました。
「VOICENCE」は、無断利用と戦うだけでなく、「公認AI」とトラスト技術による「真正性証明」を核に、適法なライセンス市場と「声の経済圏」を創造しようとする試みです。
現在でもC2PAなどの国際標準化団体により真正性証明およびそのファイル形式が推進されており、キヤノン、ソニー、NHKなどが参加しています。筆者が運営しているAICUにおいても真正性証明や対価報酬の設定などは研究開発を行っています。法整備上は「問題がない」とされることが多い、声の権利、画風や二次創作といったところにタダ乗りしている「AI海賊版」を淘汰する市場原理での「反撃」といえるでしょう。
啓蒙:法実務家と権利者に今、求められる「次の一手」とは
以上のように、10月に始まった「Sora2の挑戦状」に対し、新内閣誕生もあいまって、かなり早い段階で狼煙が上がった状態です。しかし、これは「戦いの終わり」ではなく「始まり」であると考えます。日立やソフトバンクをはじめ、多くの日本企業・官公庁からの信頼を得たサム・アルトマン氏やOpenAIが、日本と正面を切って戦うのか、それとも個々に示談を行っていくのでしょうか。
今こそ、小野田大臣の「民間企業でもしっかりとやってほしい」という呼びかけに応える時であると考えます。
本稿の提言(啓蒙)
これはかつて存在した「違法ソフトのダウンロード」と同じ構図です。「赤信号をみんなで渡れば怖くない」という考え方もありますが、生成AIは学習されてしまったら、もう2度と頭を下げる必要はなくなります。ソフトウェアのコピーとは異なり、複製物に新しい権利すら生まれる可能性があります。
AIクリエイティブ時代に「つくる人をつくる」というビジネスを推進しているAICUとしては、AIツールの進化発展は注目ですが、倫理観のあるクリエイターは、明らかに原作者の不利益につながるような道具を使いたいとは思っていませんし、グレーゾーンの多いAIモデルはそれに関わるリスクも多くなります。AIによるクリエイティビティが今後も継続的に価値を出し続けていくためにも、グレーゾーンや玉虫色の判断ではなく、「法整備」という言葉の下(もと)に立法に頼り続けるのではなく、AI時代の法律の解釈を明確にするためには、もはや司法、つまり「訴訟による判例の確立」が不可欠になるフェーズにあると感じます。
特に、第30条の4「但し書き」の適用範囲を司法の場で確定させる必要があり、text2videoにおける権利侵害、具体的には「名前タグ」による「依拠の証拠性」、商標侵害、画像だけでなく声や楽曲といった隣接権、そしてimage2videoにおいては、アップロードされた画像の翻案権、公衆送信権などが該当します。個社対応ではなく、意見集約のための集団訴訟、クラウドファンディング、CODAの動きに続く、業界横断的な集団訴訟や統一ライセンス窓口の設立を急ぐべきであると考えます。
AICUは「VOICENCE」のような「防衛」と「収益化」を両立するインフラ構築をオープンソースで推進し、有効な知財の獲得やサービスの開発を続けています。重要なのは「AIツールを使うこと」を目的にするのではなく、「つくる人が作り続けていけること」、もっと根本的な価値創出、つまり「クリエイティブAIという文化」やコミュニティ、ネットワークとエコシステムの構築です。AICUとしては、日米で3年にわたってこれを推進してきました。生成AIクリエイティブ企業として信頼あるポジションにおり、幸いなことに挑戦も案件も多くいただいていますが、日本がこのまま「Sora2」のような「赤信号をみんなで渡る」といった「戦えば勝てる訴訟」を見逃していくと、将来的にはいくらAIツールを使っても「AI貿易赤字」となることが容易に想像できる未来がやってきます。
日本が強いアニメ・漫画・ゲームといった資産や文化土壌にあぐらをかくことなく、今後も文化的・技術的・倫理的に高い視座から、学習元データをきちんと公開させて、公正な対価を支払わせる仕組みを構築しなければならないのではないでしょうか。
「うわのソラ」でバズ動画を傍観して笑っている時代は終わりました。法務・実務・ビジネスの現場から、日本のクリエイティブな文化、そこに根ざす知財を守るための具体的かつ戦略的な行動を起こす時が来ています。これは「事勿れ主義」では難しく、「戦略と挑戦」が必要であると考えます。本稿がその「啓蒙」の一助となることを願います。もし現在の生成AIが、人類全体の知やスキルの共有分配システムとして文化的に発展するのであれば、その高い位置に日本のコンテンツ産業があるのであれば、それはそれでみなさんにとって利益があるのではないでしょうか?
この話について、Change.org で署名活動を開始しました。みなさんのご意見を聞かせてください。
🔸商用AIは日本作品で利益を得ている、でも報酬はゼロ? 〜商用AIモデルに「学習データの公開」と「公正な報酬」を義務化してください〜
https://www.change.org/AI-eco-for-creators
著者プロフィール
白井 暁彦(しらい あきひこ)
AICU Japan株式会社 代表 。デジタルハリウッド大学大学院客員教授。作家/博士(工学)。「つくる人をつくる」をビジョンに、国内外を問わず、また障害の有無に関わらず、AI時代のクリエイターネットワークを構築しながら世界各地のCG/AI/XR/エンタメ技術/メディア芸術の開発現場を取材・研究・実践・発信している。 X@o_obX@AICUai
Web: https://akihiko.shirai.as
本稿はインプレス窓の杜「生成AIストリーム」への寄稿の原作であり、大幅に加筆と推敲を行なっています。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/aistream/2059356.html
https://corp.aicu.ai/ja/ai-voice-20241114
Originally published at note.com/aicu on Oct 30, 2025.

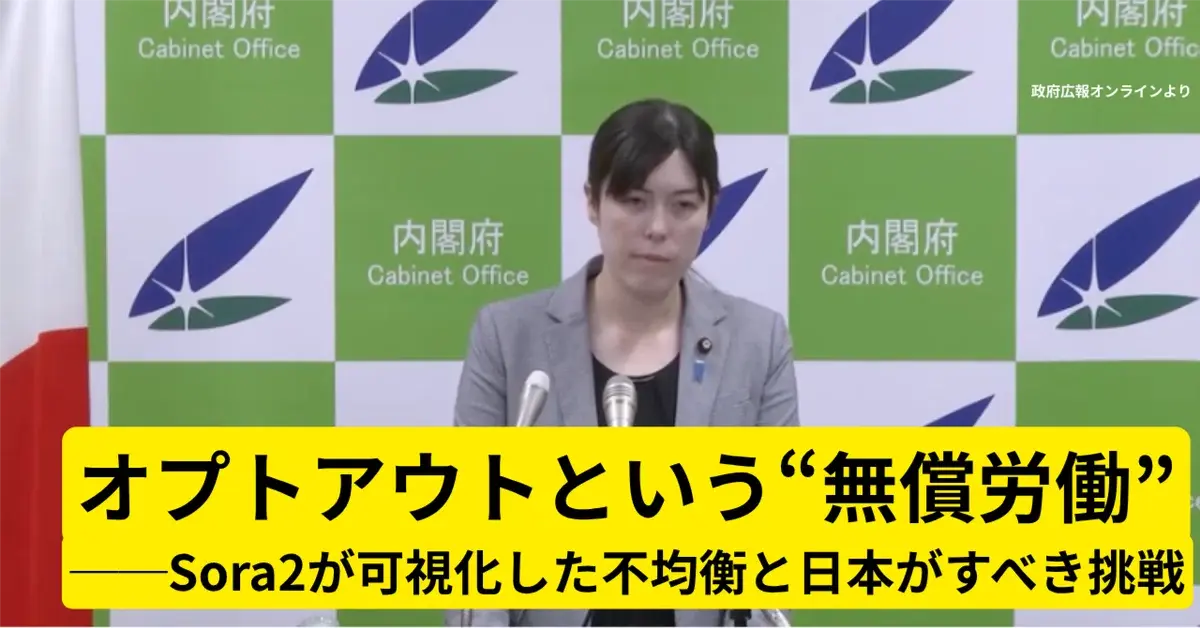
Comments